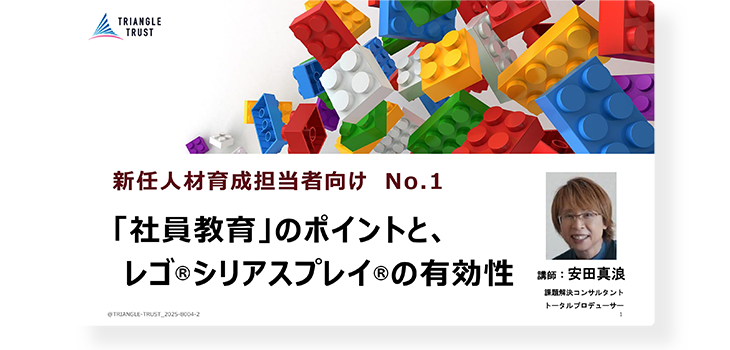YASUDA ISM
YASUDA ISM YASUDA ISM
YASUDA ISM2025.11.14 髙井 清司 | ガバナンス・コンプライアンスとは
[39] 的確な昇格・昇進は会社のレベルを上げる!
みなさんこんにちは、安田です。
トライアングル・トラスト専門家 ガバナンスコンサルタント髙井清司先生ブログ
第39回テーマは「的確な昇格・昇進は会社のレベルを上げる!」です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

先回は、「面談」を実施した「業績評価」について制度、ルールの整備も含めて私見を述べてみました。今回は、「昇格・昇進」にスポットを当ててお話したいと思います。会社にとって「昇格・昇進」は組織運営の為には重要な要素です。昇格・昇進は的確にできたかどうかで組織運営がうまくいかなくなるだけでなく、会社経営に悪影響が出ます。言い換えてみましょう。部下の管理や組織運営ができないとかマネジメントができないような人を昇進させたら、どうなるでしょうか。問題になるとか悪影響が出るなと容易に想像がつきますよね。では、これから私見をお話するに当たって、「昇格・昇進」については、“管理職になる前”と“管理職になる時”の2つに分けてお話しましょう。
≪①管理職になる前(担当、係長クラス)の昇格、昇進について≫
●学校を卒業し、入社すると研修を経て配属されますよね。日々、先輩の教育係から仕事を覚え、徐々に一人前に育っていきます。そういうプロセスの中、職能等級基準なるものがあると思いますが、一つ上の等級のレベルを目指し、日々努力します。会社の規模によっては、詳しく等級を定めてなかったり、等級基準があっても、どうなったら、一つ上の等級に昇格できるのか社員の方が把握できるような仕組みになっていない場合もありますね。私は、経営相談を受けた会社で「この仕組みでは不十分だなぁ、社員の方のやる気が心配だ。」と感じることが多々ありました。しかし、中堅企業や中小企業で完璧な制度を創り上げることはものすごく労力を伴いますので、会社の状況に応じて、どの程度のものを用意すべきかの判断は難しいです。これについては、外部のコンサルに相談することが結果、むしろ、近道かなと感じます。
●ここで最低限、会社で用意すべきもの(職能等級基準、業績評価、面談)をお話したいと思います。あくまで私の意見ですが…私は、お手伝いすることあれば、いつでもスタンバイしてますよ。
<①―1:職能等級基準>
| 一般職 | 上級一般職 | 班長職 | 係長職 | ||||
| 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
●一般職、上級一般職、班長職、係長職の4つに分け、それぞれ2段階とする。大卒の新卒の場合は2等級、高卒の場合は1等級からスタートする、そんなイメージです。
●現在の等級を卒業するのに最低何年かかるかを決め、超特急で昇進したら、係長を卒業できるかのモデルを作っておく。こういう情報があれば、「頑張り続ければ、このくらいの年齢で課長かぁ」とかイメージできますね。やる気にも繋がります。
●今後の専門職の拡大による中途入社の拡大を想定し、どの等級からスタートするかを決め、ルール化するといいでしょう。例えば、中途入社の場合、決める要素としては、前職までの経歴、処遇、強み弱みをどう組み合わせて決めるかを目安としてルール化しておくと運用しやすいと思います。
●このように決めた職能等級の枠組み毎と社内に存在する職種のマトリックスを作り、どういったことが出来るとその等級を卒業できるかを出来るだけ、具体的に書く。それがあるべき「職能等級基準」となります。大切な考え方のベースは公平・公正・平等だと思っています。
<①―2:業務評価表(会社によって色々な呼び方はあると思います)>
●上司と合意した目標、及目標値(KPI)を決め、どういう活動で目標達成したか、出来なかったかがわかるように書ける帳票が望ましい。そういった帳票になっているかを確認頂きたいと思います。
●等級が上がっていくと徐々に若手の指導係になったり、チームのリーダーになることが期待されます。供給一般職から班長になり、係長になるころには、課長という管理職に相応しいかどうかを長い期間をかけてじっくりと見極めることになりますが、評価表に管理職に相応しいかどうかがわかるよう、育成力、指導力等が記載できる欄を設けておくといいと思います。そして、職能が上がっていくにつれて、管理の評価の比率が上がっていくような枠組みがいいと思います。
●一方、社員の方の全てが管理職になる必要はありませんし、開発等の業務では競争力のある製品開発や世の中にない製品の発明など管理職になる必要はなく専門職として十分、会社に貢献してもらえます。班長、係長クラスの職能から管理職コースと専門職コースを用意することは会社の競争力に貢献できる仕組みになると思います。専門職、管理職、いずれも考え方は、公平・公正・平等です。
●そして、今まで述べました仕組みに対して、給与面をテーブルにして、皆が評価がこうなると給与はこうなるんだとわかる情報公開することがいいでしょう。体系的に整理して給与テーブルを作ることは人事は負荷的にしんどいかもしれませんが、十分、先々で効果は期待できるので是非、取り組んで頂ければと思います。
<①の3:面談>
●文化として定着すべきは「面談」です。目標の設定、活動に対するアドバイスや困りごとに相談等、人によって内容は異なりますが、上下の信頼感の構築や仕事の楽しさなど無限の可能性があるでしょう。ただ、限られた時間です。面談の仕方については、効率アップのための標準化も必要で、それが積もり積もって文化になるでしょう。大切なことは、公平・公正・平等そして思いやりの心です。是非、定着する努力をしていただきたいと思います。次に管理職にすべきかどうかの見極めについてどう考えるかを述べたいと思います。
≪②管理職になる時の昇進についての注意≫
●皆さんの会社では、管理職の昇進はどう運営されているでしょうか。私は部長時代、あまりの仕事の幅広さと量で人事評価の熟慮が少なかったせいか大きなミスをした記憶があります。ミスとは、昇進させてはいけない人を管理職にしたことでした。本来、業務の延長線上でこの程度なら管理職にしてもいいかなと判断し、昇進した途端、人のマネージができない、チーム運営ができない、報連相が甘い等が露呈し、大変苦労しました。全て、私のミスで私の責任です。今でも反省とともに思い出すことがあります。多くの会社でトップの意向や指示を受け、十分な評価もせず、昇進させてしまった例を多く見てきました。以下、留意すべき点についてお話します。
≪➂昇進選考の面談は真剣勝負!≫
●昇進制度がきちんとある中堅企業は多くないでしょう。ここで大切なことはより多くの意見を集め、昇進可否に活用することです。部下の意見、上司の意見、関連部署の意見等です。聞く意見のポイントとしては、「管理職になった場合の不具合の予測」です。私の経験からすると、部下の意見が一番参考になると思います。
●管理職になる直前の業績評価、人事考課の仕方ですが、決められた帳票に本人アピールも含めて業務の状況、部下の指導、係長としてのグループのマネジメント等を書いて、複数の面接者で面接対応すべきと考えています。それだけ、重要ですし、将来に禍根を残さない為にも重要視すべきでしょう。面談というより、選考試験と言ってもいいですね。これについては、重要なので、次回、昇進試験(アセスメント)だけにスポットを当てて述べるつもりです。
≪➃最後に≫
●ここ数回のブログ(業績評価、昇格・昇進をテーマにブログ36~38)は、一所懸命に考えて、書きました。それだけ、重要だと思っていたからです。以下、おさらいとしてポイントを書いておきますので、是非、読み返してもらえればと有難いです。参考になると思っています。
| [ブログ36]:面談成功の秘訣がテーマでした。面談を有効に活用して会社のレベルアップを図っていただければと。
[ブログ37]:業績評価ルールの大切さについてまとめました。ルールの見直しに活用いただければと。 [ブログ38]:マネジメント能力の有り無しを見極め、的確な人を昇進させ、管理職にする。それは本当に大切です。後で後悔しない為にも是非、読み返して頂ければ。特に、「昇進させてはいけない人」「管理職に向いていない人」「仕事が出来ても出世させてはいけない人」これは最後の判断材料になればと思います。 |
今日もお読みいただき、ありがとうございました。今回は「昇格・昇進」にスポットを当てて、それにまつわることについて私見を述べてみました。いかがでしたか。少しは参考になったでしょうか。ブログ36~39の内容については、自信作です。自画自賛してはいけませんね(笑)。ご活用いただければ幸いです。次回は、昇進試験(アセスメント)について経験を元にお話したいと思います。
ご期待ください。ガバナンス・コンプライアンス担当講師の髙井でした。
ガバナンスコンサルタント / 語り合うコンサルタント
髙井 清司
▶髙井 清司 先生 プロフィール
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「ガバナンス・コンプライアンス」についてのご相談ほか、
トライアングル・トラストまでお問い合わせください。
~組織づくりが企業を変える!~
トータルプロデューサー / 課題解決コンサルタント
安田真浪
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
お問い合わせや弊社事業に対する詳細説明など面談をご希望の方は、事務局までご連絡ください。
トライアングル・トラスト事務局 info@triangle-trust.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
▶YASUDA ISM(安田イズム)
※安田がプロデュースする取組み、考察ページです。
▶ 課題解決コンサルティングTRIANGLE TRUST
▶ LEGO®SERIOUS PLAY®技法と専用教材を用いたワークショップ
https://lsp.triangle-trust.jp/
▶イプロス
https://premium.ipros.jp/triangle-trust/?hub=157+4672154
▶Deliveru「新任人材育成担当者向け研修」
All Right Reserved.