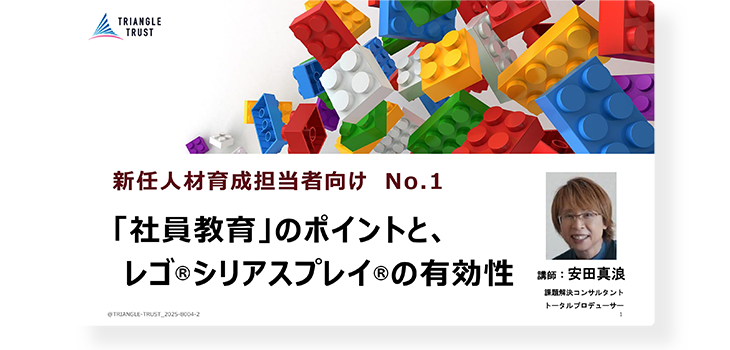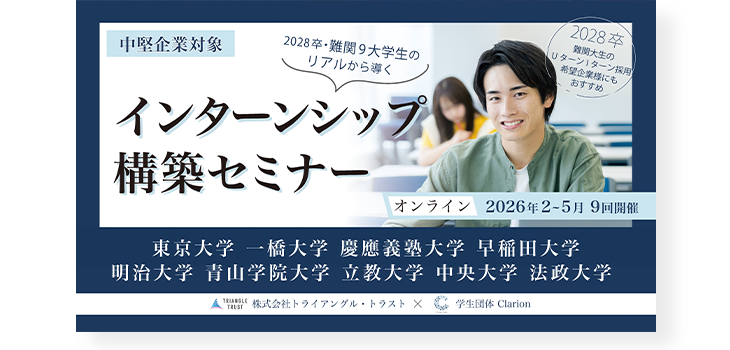YASUDA ISM
YASUDA ISM YASUDA ISM
YASUDA ISM2025.07.09 人材育成とは
社会保険料の上がり具合に恐ろしさを感じた。ー2年で驚くほど増えた負担、その実態とはー
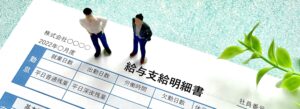
育休明けに気づいた「社会保険料」の衝撃
こんにちは、安田です。
最近、育児休業を終えて復帰したスタッフの給与明細を見て、2年間での社会保険料の値上がりに思わず絶句しました。
毎年3月と9月の手前に年金事務所から「料率変更のお知らせ」があたりまえのように送られてきます。
あたりまえのように・・・のため、上がるのがあたりまえになってしまっていて、気にもせずにいましたが、2年もすると、信じられない金額になっていたので、本当に驚きです!
そこで今回の安田イズムは、社会保険料についてまとめてみました。
そもそも社会保険料とは?
社会保険料とは、以下のような制度を支えるために納付するお金です。
・健康保険
・厚生年金
・介護保険
・雇用保険
・労災保険
現在は、賞与(ボーナス)からも社会保険料が控除されていますが、私が若かりし頃は賞与からの控除はありませんでした。
では、いつから賞与も対象になったのかというと、2003年4月からです。
1995~2003年は「特別保険料」として、保険料率が1%でした。労使折半なので、それぞれが5%ずつ負担をしていました。
それが、なぜ賞与も対象になったのかと言えば、給料と賞与額の社会保険負担の公平性を図るのが目的とされています。が、真意はどうでしょうか?
社会保険制度の歴史と変遷
さて、本題に戻りまして、社会保険制度の制度設計がいつから始まったのかを押さえて、次に、保険料率を見ていきたいと思います。
日本の社会保険制度は、戦後から段階的に整備されてきました。
1944年:厚生年金保険法施行
1947年:雇用保険制度(失業保険)創設
1961年:国民皆保険体制開始
2000年:介護保険制度開始
この制度があるからこそ安心して働ける一方で、その維持には多大なコストがかかります。
社会保険料はどれくらい上がった?──実数で見る料率の推移
では、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金」の料率を見ていきましょう。(日本年金機構公開資料より抜粋)
あわせて、消費税も表に加えてみました。
これで、負担状況がよくわかります。
| 年度 | 健康保険 料率(協会けんぽ平均) |
介護保険 料率 |
厚生年金 料率(1種) |
合計料率 (従業員負担分) |
消費税率 |
| 1950 (昭和25年) 度 | 5.00% | 0.00% | 3.00% | 8.00% (4.00%) | |
| 1955 (昭和30年) 度 | 6.00% | 0.00% | 3.00% | 9.00% (4.50%) | |
| 1960 (昭和35年) 度 | 6.30% | 0.00% | 3.50% | 9.80% (4.90%) | |
| 1965 (昭和40年) 度 | 6.30% | 0.00% | 5.50% | 11.80% (5.90%) | |
| 1970 (昭和45年) 度 | 7.00% | 0.00% | 6.20% | 13.20% (6.60%) | |
| 1975 (昭和50年) 度 | 7.60% | 0.00% | 7.60% | 15.20% (7.60%) | |
| 1980 (昭和55年) 度 | 8.00% | 0.00% | 9.10% | 17.10% (8.55%) | 1989年導入:03% |
| 1985 (昭和60年) 度 | 8.40% | 0.00% | 10.60% | 19.00% (9.50%) | |
| 1990 (平成02年) 度 | 8.40% | 0.00% | 14.30% | 22.70% (11.35%) | |
| 1995 (平成07年) 度 | 8.20% | 0.00% | 16.50% | 24.70% (12.35%) | 1997年:05% |
| 2000 (平成12年) 度 | 8.50% | 0.60% | 17.35% | 26.45% (13.23%) | |
| 2005 (平成17年) 度 | 8.20% | 1.25% | 14.29% | 23.74% (11.87%) | |
| 2010 (平成22年) 度 | 9.34% | 1.50% | 16.06% | 26.90% (13.45%) | 2014年:08% |
| 2015 (平成27年) 度 | 10.00% | 1.58% | 17.83% | 29.41% (14.70%) | 2019年: 10% |
| 2020 (令和02年) 度 | 10.00% | 1.79% | 18.30% | 30.09% (15.05%) | |
| 2025 (令和07年) 度 | 10.00% | 1.59% | 18.30% | 29.89% (14.94%) |
▶ 健康保険料
1961年に「6.3%」が、現時点では「10.0%」へ推移しています。
都道府県のばらつきがあっても、「10%」前後が徴収されており、今後の人口減からさらに負担増になる可能性が大です。
▶ 介護保険料
団塊世代がほぼ後期高齢者(75歳以上)となった2025年です。2040年には、団塊ジュニアが65歳を迎えます。
2000年に創設された介護保険は、被保険者が第1号:65歳以上、第2号:40~64歳です。
当初0.60%の料率が、2020年には約3倍の1.79%までに上昇しましたが、2025年は1.59%に引き下がりました。
これは、2024年から被用者保険の保険者ごとの納付額の算定方法の変更が起因しました。
▶厚生年金保険料
1875年に年金制度はスタート。1942年以男性労働者対象の「労働者年金保険法」が始まり、1944年には、男性事務員や女性労働者にも対象者が拡大し、「厚生年金保険法」に改定されました。
制度が発足した1942年の第1種(民間事業所に使用される者)保険料率は6.4%、その後数年は変動しましたが、1948に3.0%に落ち着いてからは数年ごとに数値が上昇し、2016年以降は18%を超える数値となりました。
各政党の「社会保障」に対する政策は?
現在、参議院選挙期間中です。「社会保障」に対する各党がの公約は、ざっとで以下の通りです。
| 政党 |
社会保障に対する公約 |
|---|---|
| 自民党 | 基礎年金の受給額の底上げほか |
| 公明党 | 基礎年金の給付底上げ |
| 立憲民主党 | 現役世代と若者の年金底上げ |
| 日本維新の会 | 現役世代1人あたりの社会保険料年間6万円引き下げ |
| 共産党 | 国民保険料引き下げ |
| 国民民主党 | 現役世代の社会保険料負担軽減 |
| れいわ新鮮組 | 介護の保険料負担軽減 |
| 参政党 | 社会保険料の負担軽減 |
| 社民党 | 月10万円最低保障年金実現 |
| 日本保守党 | 出産育児一時金の引き上げ |
各党、どちらの方向に目を向けているのかがわかりますね。
明るい未来のために ── 増やす努力、減らす努力
社会保険料の上昇は避けられない現実の一部かもしれません。
でも、未来の世代にこの重い負担をそのまま背負わせてよいのでしょうか?
私たちは、「増やす努力(雇用・収入・経済力)」と「減らす努力(制度改革・見直し)」の両立を進める必要があります。
若者に希望ある未来を残すために、今、真剣に考えるときです。
~組織づくりが企業を変える!~
トータルプロデューサー / 課題解決コンサルタント
安田真浪
トライアングル・トラストは、組織における各種課題解決のお手伝いをしています。
オーダーメイドプログラムで、担当者様と一緒に取り組んでいます。
お気軽にご相談ください。
▶ 課題解決コンサルティングTRIANGLE TRUST
▶ LEGO®SERIOUS PLAY®技法と専用教材を用いたワークショップ
https://lsp.triangle-trust.jp/
▶イプロス
https://premium.ipros.jp/triangle-trust/?hub=157+4672154
▶Deliveru「新任人材育成担当者向け研修」
All Right Reserved.